
Pythonでプログラムを作成する際に、変数や値の型を確認したい場面は頻繁に発生します。
その中でも isinstance() は「オブジェクトの型を判定する」「条件分岐で型に応じた処理をする」など、安全で柔軟な型チェックを行うための基本的な組み込み関数です。
この記事では isinstance() の基本的な使い方から、活用シーン、注意点までをわかりやすく丁寧に解説します。
isinstance()とは?
isinstance() は、Pythonの組み込み関数で、指定したオブジェクトが特定の型(クラス)のインスタンスかどうかを判定する機能を持ちます。
第一引数にチェックしたいオブジェクト、第二引数に型(またはタプルで複数の型)を指定して、該当する型であれば True、そうでなければ False を返します。
Pythonでは、動的型付けの特性上、変数の型が実行時に決まるため、isinstance() を使って安全な型チェックができます。
基本的な使い方
まずは、基本的な型判定のコードを見てみましょう。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
# 様々な型の値を用意 number = 42 text = "Hello, World!" items = [1, 2, 3, 4, 5] data = {"name": "田中", "age": 30} # 型判定を実行 print(isinstance(number, int)) # True print(isinstance(text, str)) # True print(isinstance(items, list)) # True print(isinstance(data, dict)) # True print(isinstance(number, str)) # False |
このコードでやっていることは:
- 各種データ型の変数を準備
isinstance()で各変数の型を判定- 判定結果(True/False)を出力
- 実際の型と異なる型での判定も確認
変数の実際の型と一致している場合は True、異なる場合は False が返されます。
具体例:条件分岐での型に応じた処理として使う
isinstance() は条件分岐で型に応じた処理を分ける際にも頻繁に使われます。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
def process_data(data): if isinstance(data, str): print(f"文字列を処理: {data.upper()}") return data.upper() elif isinstance(data, int): print(f"整数を処理: {data * 2}") return data * 2 elif isinstance(data, list): print(f"リストを処理: 要素数 {len(data)}") return len(data) else: print(f"未対応の型: {type(data)}") return None # 異なる型のデータで関数を呼び出し process_data("python") # 文字列を処理: PYTHON process_data(25) # 整数を処理: 50 process_data([1, 2, 3]) # リストを処理: 要素数 3 |
このように:
isinstance()で引数の型を判定- 型に応じて適切な処理を実行
- 未対応の型の場合はエラー処理
この一連の処理で、型安全な関数を作成できます。
isinstance()で使える型指定の例
Pythonでは、以下のような形式で型を指定できます。
| 型の種類 | 指定方法 | 例 |
|---|---|---|
| 基本型 | int, str, float |
isinstance(x, int) |
| コレクション | list, dict, tuple |
isinstance(x, list) |
| 複数型 | タプルで指定 | isinstance(x, (int, float)) |
| カスタムクラス | クラス名 | isinstance(obj, MyClass) |
| 抽象基底クラス | collections.abc |
isinstance(x, collections.abc.Iterable) |
型の確認は、Python の type() 関数や IDE のヒント機能でも確認できます。
isinstance()の引数オプション
isinstance() の基本的な構文は以下の通りです:
|
1 2 |
isinstance(object, classinfo) |
- object:型を確認したいオブジェクト
- classinfo:型(クラス)またはタプルで複数の型を指定
複数の型をチェックする場合:
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
# 数値型(int または float)かどうかをチェック value = 3.14 if isinstance(value, (int, float)): print("数値型です") # 文字列型かリスト型かをチェック data = "test" if isinstance(data, (str, list)): print("文字列またはリストです") |
また、継承関係も考慮するため、親クラスの型でもTrueを返します。
isinstance()を使うときの注意点
type()との使い分けに注意
isinstance() と type() の違いを理解して使い分けることが重要です。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
class Parent: pass class Child(Parent): pass obj = Child() print(isinstance(obj, Parent)) # True(継承を考慮) print(type(obj) is Parent) # False(厳密な型チェック) print(type(obj) is Child) # True |
isinstance() は継承関係を考慮するため、通常はこちらの使用が推奨されます。
None値のチェックに注意
None の型チェックには注意が必要です。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
value = None print(isinstance(value, type(None))) # True print(isinstance(value, str)) # False # より読みやすい書き方 if value is None: print("値がNoneです") |
None チェックには is None を使う方が一般的で読みやすいです。
パフォーマンスに注意
頻繁に型チェックを行う場合、パフォーマンスに影響することがあります。
設計時に型チェックが必要な箇所を最小限に抑え、型ヒントやIDEの静的解析も活用しましょう。
|
1 2 3 4 |
# 型ヒントを使用した関数定義 def calculate(x: int, y: int) -> int: return x + y |
まとめ
今回はPythonの isinstance() 組み込み関数について紹介しました。
isinstance()は指定したオブジェクトの型を判定するための基本関数- タプル指定で複数の型を同時にチェックでき、柔軟な型判定が可能
- 条件分岐→型判定→適切な処理といった一連の操作も簡単に実現できる
- 継承関係を考慮するため、通常は
type()よりもisinstance()の使用が有効
isinstance() をマスターすれば、エラー処理、データバリデーション、API のレスポンス処理など、さまざまな場面で安全な型チェックを行えるようになります。
Pythonでの堅牢なプログラミングを行う基本スキルとして、ぜひしっかり理解しておきましょう。

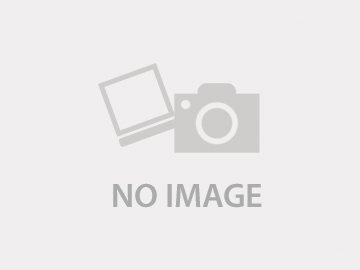
![【Python】None の場合のエラーを防ぐ or [ ]の使い方をわかりやすく解説!](https://pythonaiclarifydoubts.com/wp-content/uploads/2025/06/Python-300x169.png)